top of page
検索


ポストコロナ時代の教育を考える⑨:予想される研修業界の地殻変動
前回は、研修業界の地殻変動の予測を述べました。 私たちは、仕事を行うためには必要な知識とスキルを習得しなければなりません。 これはどんな時代でも不変です。 しかし、私たちの働き方や場所、テクノロジーの発展によって、習得方法は大きく変わるでしょう。...

田口光彦
2021年3月8日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える⑧:リアル研修のオンライン化では意味がない
コロナ禍によってほとんどの研修がオンラインで実施されました。 2020年度は必要に迫られ、リアルで行っていた研修をオンラインで実施する形がとられたのではないでしょうか。 オンライン研修2年目以降は、オンライン研修の質が問われ、研修業界の地殻変動が始まるはずです。...

田口光彦
2021年3月5日読了時間: 2分
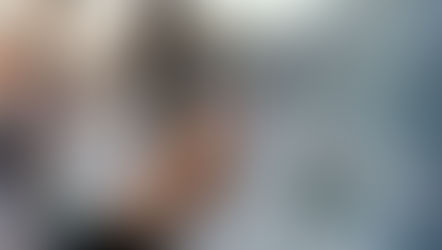

ポストコロナ時代の教育を考える⑦:新入社員のための毎月教育(その3)
今回は、新入社員のための毎月教育のうち「職場自慢:職場の自慢の技術や技能を動画撮影」について、その意味や進め方をご紹介します。 職場には必ず自慢の技術や技能があるはずです。 新入社員の立場で、世の中の汎用的なスキルと自慢できる技術や技能の区別をするのは至難の技です。...

田口光彦
2021年3月4日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える⑥:新入社員のための毎月教育(その2)
今回は、「TYWレポート:自己成長のPDCAを回すためのツール」についてご紹介します。 リフレクション(内省)は、自分自身の仕事に対する考え方や行動を客観的に振り返ることをいい、 成長スピードを飛躍的に高める方法です。 リフレクションのツールとして広く使われているものに「Y...

田口光彦
2021年3月4日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える⑤:新入社員のための毎月教育(その1)
コロナ前に行われていたフォローアップ研修の参加者の視点での目的を確認してみたいと思います。 1. 導入研修で学習した「仕事の基本」の実践度を確認する 2. 仕事上で困っていることを解消する(仲間も同じように困っていること確認する) 3....

田口光彦
2021年3月3日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える④:オンラインだからできること
リアル研修とオンライン研修における費用で圧倒的に違うのが、宿泊代を含めた交通費です。 事業所が全国展開して企業にとって、研修における交通費は大きな金額となります。 私がお世話になっている企業では、研修をオンライに変えることで節約できた交通費を...

田口光彦
2021年3月2日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える③:オンライン研修でリアル研修以上の成果を上げる(その3)
ポストコロナ時代の研修モデルを実施することで、以下のような変化が生まれました。 · 反転授業を行うことで研修への参加姿勢が極めて高くなった · コロナ前と比較して、職場実践の実践度も内容も高まった · コロナ前と比較して、職場実践レポートの提出率や納期遵守率が高まった...

田口光彦
2021年3月1日読了時間: 1分


ポストコロナ時代の教育を考える②:オンライン研修でリアル研修以上の成果を上げる(その2)
前回は、「反転授業→実務適用→アクションラーニング→相互学習」 のポストコロナ時代の研修モデルの前半をお話ししました。 今回は、その後半をお伝えします。 実務適用を行うオンライン研修の最後には、職場実践計画を立て、 全員に職場実践の自己宣言を行ってもらいます。...

田口光彦
2021年2月26日読了時間: 2分


ポストコロナ時代の教育を考える①:オンライン研修でリアル研修以上の成果を上げる(その1)
コロナ禍によって企業における研修は、大きく変わりました。 単にリアルで行っていた研修が、オンラインに変わることを意味してはいません。 コロナ禍で行う教育・研修を、人材開発の変革の第チャンスとして捉え、 緊急事態宣言下で行う教育・研修に関しては、どんなことに挑戦しても“失敗は...

田口光彦
2021年2月25日読了時間: 2分


戦略人事に転換する⑧:世界の人事制度の潮流
パフォーマンス・マネジメントの変化の潮流を3つの層でとらえると以下のとおりとなります。 1.人事制度や運用するための仕組み・ツールの変化 ①ノーレイティング(評価段階付けを廃止する) ②ノーカーブ(あらかじめ定められた分布率に当てはめる相対的評価を廃止する...

田口光彦
2021年2月24日読了時間: 2分


戦略人事に転換する⑦:評価制度の本質を考える
アメリカ企業の取り組みから、 社員のパフォーマンスの測定(人事評価)をやめると業績が40%向上する ということが2015年のATDで発表され、アメリカ企業の1/3以上が実施しています。 それでは、何で人事評価をやめると社員のパフォーマンスが向上するのでしょうか?...

田口光彦
2021年2月22日読了時間: 3分


戦略人事に転換する⑥:日本の人事制度の特徴(その2)
日本企業は、評価のために等級制度を用いてきました。 下図が伝統的な人事の枠組みです。 VUCA時代の到来と人間社会の成熟によって、 人事の枠組み自体が制度疲労を起こしているのかもしれません。 以下の項目を是非チェックしてみたいものです、...

田口光彦
2021年2月19日読了時間: 1分


戦略人事に転換する⑤:日本の人事制度の特徴(その1)
かつての日本企業は、「長期的視野に立った経営」と「人間中心(尊重)の経営」のコンセプトのもとで経営しており、そこから日本的人事システムが形成されていきます。 日本の労使関係は、職能資格制度によって安定的に構造化され、 階層的平等化をつうじたブルーカラーのホワイトカラー的統合...

田口光彦
2021年2月18日読了時間: 2分


戦略人事に転換する④:日本企業における戦略人事のあり方
下の図は、デイブ・ウルリッチ教授が提唱する人事の機能をもとに、日本の人事に適応したものです。 オペレーション中心の人事から業績に貢献する人事に変わるためにも、 ビジネスパートナー機能を強化することが求められます。 ビジネスパートナー機能とは、各部門や社員に寄り添い、...

田口光彦
2021年2月16日読了時間: 2分


戦略人事に転換する③:ウルリッチ教授から学ぶ戦略人事
デイブ・ウルリッチ教授を中心としたグループは、人事の存在を以下のように唱えています。 日本の人事が、取り組む方向を明確に描くことができます。 競争優位の源泉として、企業に多大な付加価値をもたらす人事にはそのような潜在能力があると 我々は信じている。...

田口光彦
2021年2月15日読了時間: 2分


戦略人事に転換する②:日本の人事がオペレーション中心に移行した背景
平成の時代を振り返るとバブル経済の最終局面から始まり、1991年にバブルが崩壊し、 日本企業は三つの過剰(雇用・設備・債務)(注1)の克服に取り組むことが最重要課題でした。 それからも幾多の困難な状況はありましたが、2005年にバブルの負の遺産である三つの過剰も...

田口光彦
2021年2月12日読了時間: 2分


戦略人事に転換する①:戦略人事とは何か
日本においても戦略人事への転換が叫ばれて、20年以上の歳月が経過しています。 世界では、「CHRO」「CHO」など人事の責任者が経営に不可欠な人材となっていますが、 これは人事が戦略人事に転換した結果の象徴です。 戦略人事とは、1990年代にアメリカの経済学者デイブ・ウ...

田口光彦
2021年2月10日読了時間: 1分


高生産企業に転換するため⑧:ムリへの挑戦
3ムの最後のターゲットが「ムリ」です。 ムリは、いままでの考え方ややり方では実現できないことが対象となります。 ムリへの挑戦は、問題解決そのものといってもいいでしょう。 一般的に問題とは、あるべき姿と現状のギャップをいいます。 そのギャップを埋めるために方法改善を行います。...

田口光彦
2021年2月8日読了時間: 1分


高生産企業に転換するため⑦:ムラの排除
ムラとは“仕事上で発生するバラツキ”をいいます。 バラツキは、人によるバラツキ、場所や時間によるバラツキ、作業環境の違いによるバラツキなど、色々な場面で発生します。 仕事のバラツキをなくすためには、仕事の標準化とメンバーのスキルアップ(トレーニング)に取り組む必要があること...

田口光彦
2021年2月5日読了時間: 3分


高生産企業に転換するため⑥:ムダの排除(その2)
ムダの排除を考える上で便利なツールがアメリカ第34代大統領ドワイド・D・アイゼンハワー氏が考案した「アイゼンハワー・マトリックス」です。 このマトリックスは、名著『7つの習慣』で紹介され、有名になりました。 自分の仕事を4つの象限に分けて書き出してみましょう。...

田口光彦
2021年2月4日読了時間: 1分
bottom of page
